こんにちは! kecchiblogへようこそ。
北海道の長い冬。その厳しい寒さの中で、心と体を温めてくれるのが、燃え盛る炎が美しい「薪ストーブ」です。
僕の自給自足の暮らしにおいても、薪ストーブは欠かせない相棒です。
しかし、薪ストーブのある暮らしには、避けては通れない大きな課題があります。
それは「大量の薪を、どうやって保管するか」という問題。
今回は、僕が廃材と知恵を総動員して作り上げた、我が家の冬の生命線、「自作の薪棚」について、その設計思想から完成までをご紹介します。
第一章:必要から生まれた、究極の設計
僕の薪棚作りの原点は、開拓中に生まれる大量の木々でした。
廃材の山から出てきた再利用不可能な木材、土地を切り拓く中で伐採した木や枝…。
それらを保管するため、当初は廃材で小さな小屋を作っていましたが、薪ストーブのある暮らしを本格的に考えるなら、それでは全く足りません。
雨に濡れず、大量の薪をストックできる場所が必要でした。

僕が設計で最も重視したのは「薪の乾燥」です。
薪ストーブの性能を最大限に引き出すには、十分に乾燥した薪が不可欠。
そのため、壁は作らず、北海道の風が通り抜けることで、薪が自然に乾燥していく構造を目指しました。
骨組みには、ハウス兼ガレージでもその頑丈さを証明済みの「角パイプ」を。
そして、壁の部分には、知人から譲り受けたビニールハウスの細いパイプを切断・溶接して使うことにしました。
木材で壁を作ると風を塞いでしまいますが、パイプなら薪が落ちるのを防ぎつつ、乾燥に不可欠な風通しも確保できる。
まさに一石二鳥のアイデアでした。
第二章:一人で挑む、基礎からの創造
この薪棚も、建設は基本的にほぼ一人。特に大変だったのが「基礎」でした。
水平を保ち、重い薪の重量を支えるための土台です。
しかし、ここでも幸運が訪れます。廃材の山となっていた古い家の解体跡地から、床を支えていたと思われるコンクリート製の束石(つかいし)が大量に出てきたのです。まさに宝探し。
足りない分はその辺に落ちていた石で補い、セメントなどを使うことなく、この廃材の束石だけで頑丈な基礎を組み上げることができました。

基礎さえできてしまえば、あとは得意の溶接作業。
角パイプと再利用した細いパイプを組み合わせ、骨格を組み上げていきます。

第三章:完成した「要塞」と、薪ストーブのある暮らし
そして、ついに我が家の冬の生命線が完成しました。

この薪棚の収容能力は、約18立米。北海道の一般的な家庭で一冬に消費する薪は5〜10立米と言われています。
つまり、この薪棚は北海道の厳しい冬を余裕で乗り越え、さらに次の冬の分まで蓄えておけるほどの、まさに「要塞」なのです。
さらに、この設計には思わぬ副産物もありました。屋根の下にできた三角形のスペースが、片付け中に出てきた使えそうな長い木材などを保管するのに、驚くほどぴったりだったのです。
計算ではなく、偶然生まれたこの収納スペースも、今では重宝しています。
この薪棚があるからこそ、安心して薪を作ることができます。

そして、十分に乾燥させた薪は、室内で冬の暮らしを豊かにしてくれます。

そして何より、薪ストーブには理屈抜きの魅力があります。
キャンプで焚き火を囲んだことがある人なら、きっと分かってくれるはず。
ゆらめく炎をただ静かに眺めているだけで、心が落ち着き、体の芯からリラックスできるのです。
エアコンの人工的な暖かさとは全く違う、この生きた炎の温もりと魅力に惹かれて、ついついストーブの近くでくつろいでしまいます。

薪棚を作ることは、単なるDIYではありませんでした。
それは、北海道の厳しい自然と向き合い、冬という季節を豊かに楽しむための、「覚悟」と「知恵」を形にする作業だったのです。
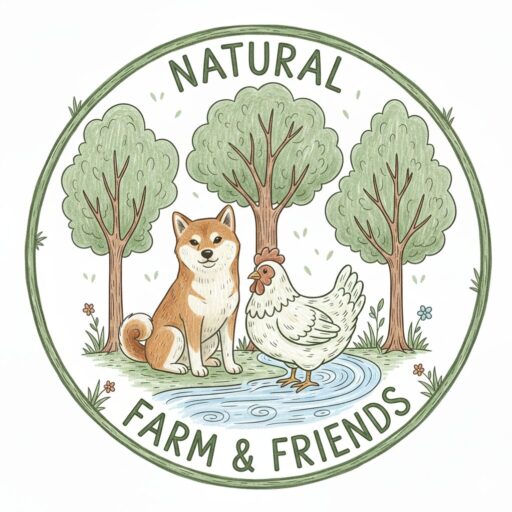





コメント