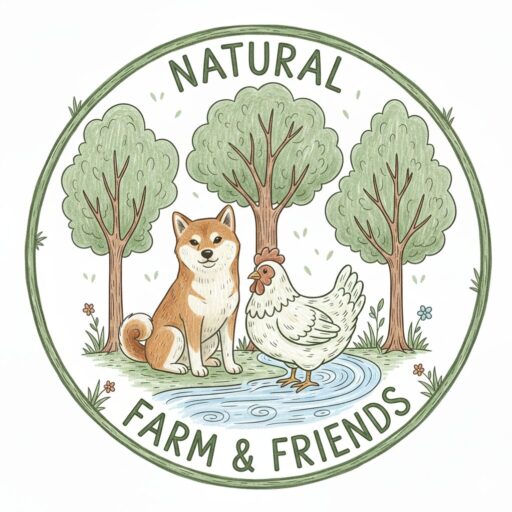はじめまして。
このブログ「道南自給ライフの記録」を見つけてくださり、ありがとうございます。
運営者のけっちです。
僕は今、北海道の南西部に位置する、自然豊かなこの土地で、鶏や犬と共に自給自足の暮らしに挑戦しています。数年前まで、まさか自分がこんな生活を送るとは、夢にも思っていませんでした。
このページでは、僕がどんな人間で、どのような経緯でこの暮らしにたどり着いたのか、少し長くなりますが、その物語をお話しさせてください。

第一章:原因を探求し続けた会社員時代
高校を卒業後、僕は一部上場企業に就職しました。
自分で稼いだお金で車を買い、便利なものを揃え、毎週末のようにスキー場へ繰り出す。ごく普通の、安定した毎日でした。
そんな僕の人生が、大きく舵を切り始めるきっかけとなったのが、入社当初から希望していた「設備管理」という部署への異動です。
ここでの主な仕事は、工場にある巨大なプレス機械のトラブル対応。プログラム、電気、油圧、空圧、メカ…機械に備わるすべての知識が求められる仕事でした。最初は知識不足で、毎日が必死の勉強でした。
この仕事で最も難しかったのは、ただ「直す」ことではありませんでした。その前段階である**「原因の特定」**です。オペレーターから状況を聞き、考えられる原因を洗い出し、現物を確認して、やっと修理作業に取り掛かる。メカ的な知識には自信がありましたが、その前段階の思考プロセスが、これほど大変だとは思いませんでした。
しかし、3年も経つ頃には、トラブルの電話が鳴れば「あーはいはい、これね」と、即座に原因が頭に浮かぶようになっていました。この経験が、僕の思考の仕方を根底から変えてしまったのです。
第二章:一つの違和感と、人生の天秤
設備管理として一人前になった頃、世界はコロナ騒ぎの真っ只中にありました。
僕の頭はすっかり「設備管理モード」です。物事の経緯や情報を調べていくうちに、世の中の流れに対して、ある種の「違和感」を覚え始めました。
会社という組織に属していれば、マスクの着用やワクチンの推奨は当たり前。けれど、周りに僕と同じような違和感を口にする人はいませんでした。その時、ふと思ったのです。
「このまま何十年もここに勤めていて、僕の人生は本当に楽しいんだろうか?」
その問いをきっかけに、僕は様々な情報をかき集め始めました。そして、ある一つの情報が目に留まります。**「自然農法」**です。
耕さない。肥料を使わない。草はそのまま。それまで僕が持っていた農業の概念が、180度ひっくり返りました。ちょうど食品添加物の危険性を知ったばかりだったこともあり、「こんな農法があるのか!」と衝撃を受けました。
その時、僕の頭に、父親の実家が誰も住んでおらず、その近くに広大な土地があるという事実が、パズルのピースのようにはまりました。
車中泊の経験から、どんなボロ家でも住める自信がある。
2町もの土地があるなら自然農法を自分で実践できる。
仕事で培った電気や機械の知識があれば、自給自足ができるかもしれない。
最悪失敗してもこの知識と技術があればどこでも働きに行ける。
このままサラリーマンを続ける人生と、自給自足の人生。二つを天秤にかけた時、僕の中で答えは決まっていました。
第三章:最高の相棒たちとの、今の暮らし
頼れるパートナー、縄文柴犬
自然農法を調べる中で知ったのが、縄文柴犬の存在です。その運動能力と、何より野生的なスタイルのかっこよさに惹かれました。そんな中、鶏を譲ってくれた養鶏場の方が飼っていた犬の姿に、僕は心を奪われます。
その犬は、飼い主が住む家までついてくることなく、養鶏場の周りで鶏の敵となる害獣から、自らの判断で鶏たちを守っていたのです。「犬は、こんなにも賢いのか」と感動しました。鶏を守り、時には山で熊などから僕自身を守ってくれるパートナーが欲しい。そう思い、ブリーダーさんから彼を迎え入れました。

小さな働き者たち、鶏
僕にとって鶏は、ただ卵を産んでくれるだけの存在ではありません。彼らは癒しであり、生ゴミを食べてくれる掃除屋であり、裏庭の草を刈ってくれる草刈り機であり、その糞は最高の天然肥料になります。昔の人が「庭には鶏」と言っていた理由が、今ならよくわかります。

理想と現実、そして未来へ
もちろん、良いことばかりではありません。広大な土地の開拓は、肉体的に本当に大変です。草を刈り、木を切り、畝を作る。すべてが体力勝負。野生動物に作物を食われるなど、想定外のことも日常茶飯事です。
それでも、この暮らしを選んで良かったと心から思います。一番の理由は、生活コストが圧倒的に低いこと。おかげで、以前のように毎日働きに出なくても生活ができ、自分のペースで物事を進められる。このストレスのない日々は、何物にも代えがたいものです。(逆に言えば、サボるのも簡単なので、常に自分との戦いですが笑)
今はまず、僕自身が完全に自給自足できる状態になることを目指しています。そして、その段階が終わったら、この経験や成果を、僕と似たような考え方を持つ人、共感してくれる誰かに、お裾分けできたらなと考えています。
このブログが、そんな未来への第一歩です。
これから、どうぞよろしくお願いします